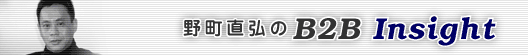新しい購買業務のあり方
それでは直接材購買における「電子調達」等の活用による新しい購買業務はどうあるべきであろうか?ここでは「新しい購買業務のあり方」についてプロセス、ITの活用、体制面の3つの視点での考え方を示し、具体的な活用事例について述べたい。
・ソーシングプロセスの整備
図7はあるべきソーシングプロセスの姿である。BOM(Bill of Material:部品表)の作成〜ソーシングリストの作成、ソーシングプランの作成、RFQ(Request for Quotation:見積り依頼)作成〜展開、回答入手〜交渉、ソーシング決定と至るプロセスフローを横軸に示している。この中で特に赤字で示しているのは戦略的な購買業務であり、青字で示しているのはITツール等の「電子調達」ツールが有効に活用できる事項である。
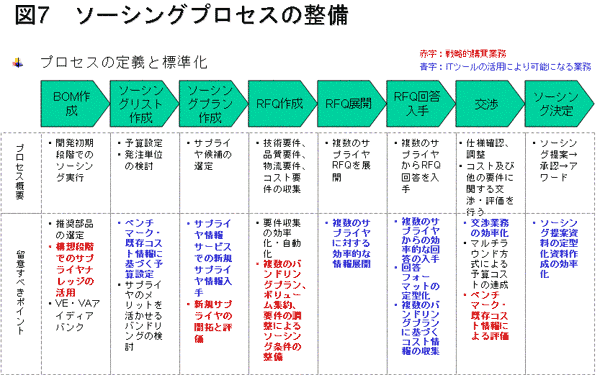
端的に言うと戦略的な購買業務とは新規サプライヤの開拓とソーシングへの招待、要求元との調整等による競争環境を確保できるようなRFQ(見積り依頼)の作成につきる。競争環境や仕様条件、手配単位やボリュームの集約などの業務を行うことでサプライヤが競い合えるソーシング環境を如何につくるかということ、サプライヤ育成等のサプライヤ戦略の計画・実行を行うことが重要な戦略業務であるにも関わらず、企業によっては手配や納期管理、検収業務まで購買担当者が行っている会社もあり、現実的には非戦略的な業務時間の比率が非常に高く実務に追われて戦略的な業務の遂行ができていないことが実態である。
もう一つの重要なポイントは入手した見積りの妥当性を評価する点である。直接材であればコスト構造の比較まで行いコスト分析・比較を行った上で価格決定に至る。この際、比較する対象を特定品目でのサプライヤ間のコスト比較だけに限定せず、過去の契約価格や見積価格、他社の購入価格レベルとの比較にまで広げることで蓄積された購買情報を有効活用し価格の妥当性評価に使用していくことが可能となる。
米国の先進企業では電子調達ツールを活用し、発注業務等を自動化・効率化すると共に、今までの人員を分析要員(アナリストバイヤー)として育成している。従来でもシビアな価格交渉を続けてきた品目であるだけにコスト情報、技術情報を「見える化」しコスト分析を行なう能力の育成はこれからの購買業務に必須であると考えられる。
・電子調達ツールの活用
「電子調達」ツールの活用においてはオープン型のサプライヤ情報提供サービス、e-RFQと言われる電子入札ツール、交渉の自動化のツールであるオークション、コスト情報やサプライヤ情報データベース等の活用が先進的な取組みとして上げられる。
それを簡単にまとめたのが図8である。基本的にはe-RFQはソーシングプロセスの全体の流れをサポートし、オークションやサプライヤ情報提供サービスはそれをサポートするツール、コスト情報、サプライヤ情報は部品の選定・サプライヤ選定・価格決定等の意思決定をサポートするツールと位置づけられる。
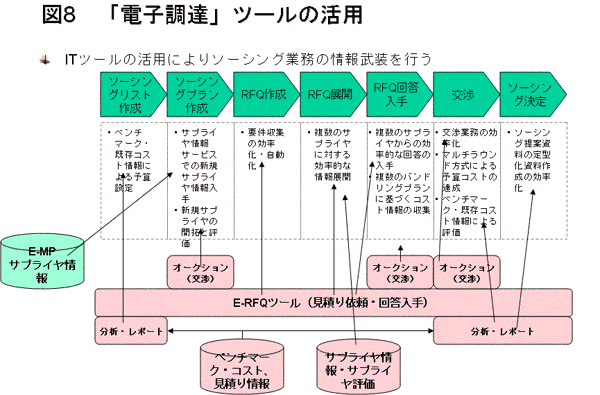
・体制の改革
体制面で重要なポイントはユーザー、バイヤー、仕様設定者の三権分立を確立することにある。多くの企業では通常新製品開発の初期の段階で設計者が特定のサプライヤと検討を進めていて、仕様の設定時にはその特定のサプライヤしかできない設計になっているというケースが良くある。この場合最終的な発注権限は購買部門が持っているものの、サプライヤ選定自体は既に仕様設定者が行っていると言える。仕様設定者はユーザーに対し要件を満たすためのリスクを回避する行動をとる指向があるため、不必要に高い仕様を設定したり、サプライヤの言いなりになったりして、結果的に競争環境が整備されないケースも多い。このような事態を防ぐために三権分立を確立し、購買部門の早期のインボルブや意志を伝えるための推奨部品・サプライヤデータベース等のインフラの整備が重要になってくる。
e-RFQ活用事例
e-RFQはソーシング全体の流れを自動化し、透明性・公平性を確保するためのツールである。一方で現状のFAXやメールでのやり取りを単に電子化するだけでは大きな効果はもたらされない。e-RFQの効果的な活用方法はサプライヤ情報との連携とコスト情報との連携である。(図9)
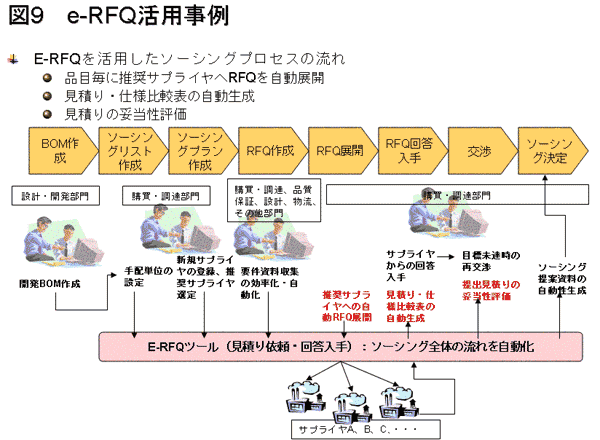
サプライヤ情報との連携は品目別に見積り引き合いする推奨サプライヤの情報を紐付けておき、ある品目の引合い情報に関しては必ず事前に決められた複数社のサプライヤに展開を義務つけておくということである。この業務の流れを標準化することで購買担当者が外部から材やサービスを購入する時の基本ルールが整備され、複数のサプライヤからのソーシングを義務付けることが可能となる。
現在、ある公的団体でe-RFQを有効活用している事例では、従来であれば要求部門がよきに計らえ、的な購買プロセスを行っていたが、e-RFQのツールを活用することで要件の定義能力自体が向上したというメリットを上げている。
自治体等の公共団体では一定の金額以上の購買案件に関しては公開入札や指名競争入札などがルール化されており従来からソーシング活動は行われている。e-RFQの活用もそういう点から馴染み易いのではあるが、従来のFace to Faceの業務では曖昧な仕様の定義を現場説明会の実施等で補っていることが多かった。この団体でも従来であれば入札説明会の場所の確保から入札説明会の実施、現場説明会の実施などの業務にe-RFQを活用することで効率化を実現すると共に、過去のRFQを参考にテンプレートを作成することでRFQの質が向上し、アシスタントの方でも購買業務を進めることが可能になったと聞いている。
e-RFQのコスト情報との連携という点では、見積りの妥当性評価への活用が有効である。ある企業では入手したコストレベルの妥当性があるものかどうかベンチマーク手法で妥当性をチェック、ソーシング決済資料の自動作成につなげている。
ここでの重要なポイントはどのようにコストを分析し比較を行うかという手法である。従来コスト分析はコスト構造をブレイクダウンし、コストテーブルを作成し、比較できるような指標に落とし込んで妥当性の評価を行っていた。また汎用品などは機能同等品という属性で代替品を特定し比較を行うことが可能であった。カスタマイズ部品の場合このような分析は難しく複雑性が増す。この企業では非常に単純化したコストドライバーを設定し、コストドライバー単位でコストの比較を行いコストの妥当性を検証している。
このようにe-RFQを活用することでソーシングプロセスの標準化、効率化を実現している事例が出始めている。
オークション活用事例
オークションは交渉業務の自動化のためのツールである。コスト低減のためのツールという誤解が多く見られるが、本当の効果はソーシング業務の標準化、効率化と短期間での市場価格の取得の2点に集約される。
但し、オークションは価格情報のみを入手するツールであり、全ての品目・ソーシングプロセスで活用することは難しい。先進的な企業ではe-RFQをサポートする形でオークションを上手く活用している。
オークションの活用パターンとしては3通りある。(図10)1つ目のパターンは広く門戸を開いて候補サプライヤを絞り込むケースでの活用方法である。例えば「電子調達」サービスの一種であるオープン型e-MPのサプライヤ情報提供サービスで候補のサプライヤをいくつかピックアップし、オークションを実施し数社に絞り込んだ上で、e-RFQで見積り依頼を展開、ソーシングを実行するという活用方法である。
2番目の活用方法はRFQをe-RFQで展開しコストの回答入手にオークションを活用するという方法である。この活用方法では仕様が固まっている品目でないとオークションの活用は難しく、汎用品や規格品、間接材などでのオークション活用に限定される。
3番目の活用方法はe-RFQでRFQを事前展開し、回答を入手、目標コストが達成されていないため条件等の見直しを行った上で最終決定のためにオークションを活用する方法である。現在のオークションの活用としてはこの活用事例が多い。
オークションはあくまでもしっかりしたRFQを前提として、人の交渉によるバラつきをなくしソーシング活動による原低効果を綺麗に引き出すツールである。企業毎の購買ポリシーや適用する品目、プロセス毎に上手く活用すれば効率化と限界価格の引き出しに大きな効果をもたらす「電子調達」ツールである。
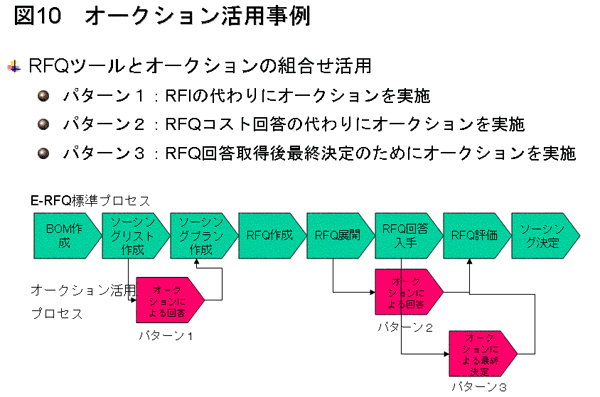
最後に
直接材に関する調達業務改革の課題として「新たなコスト低減の為のしくみづくり」を取り上げたが、これは属人性を排除し、ソーシング能力とコスト分析能力を向上することが重要であることを述べてきた。この2つの能力を向上させる為に「電子調達」は非常に有効であり、業務改革を支援する形で水面下でその活用が着実に進展している。一部の先進的な企業ではトライアンドエラーを続け自社にとっての「電子調達」の有効な活用方法を見出し、あたかもFAXやe-メールを使うように「電子調達」活用の定着化に進んでいる事例がでてきている。
但し、現状このような「電子調達」の活用についての最も大きな課題の一つはバイヤーの意識改革であり、購買・調達業務の近代化である。自ら業務改革を進めていく姿勢、自ら新しい技術、サプライヤの情報を積極的に収集し、社内におけるバイヤーの地位向上につながるような姿勢を持つことがその第一歩である。
株式会社アジルアソシエイツ 代表取締役社長 野町 直弘